遺贈

遺贈とは
遺言は、遺言者の死亡によってその効力が生じます。
遺贈とは、この遺言によって自分の財産を特定の人に無償で与えることをいいます。遺贈の相手である、受遺者は、相続人及び相続人以外の第3者のみならず個人以外の会社等の法人でもかまいません。
被相続人が死亡した時に、受遺者は生存している必要があります。遺贈には代襲相続がないため、受遺者が先に死亡していた場合は、遺贈は無効となります。
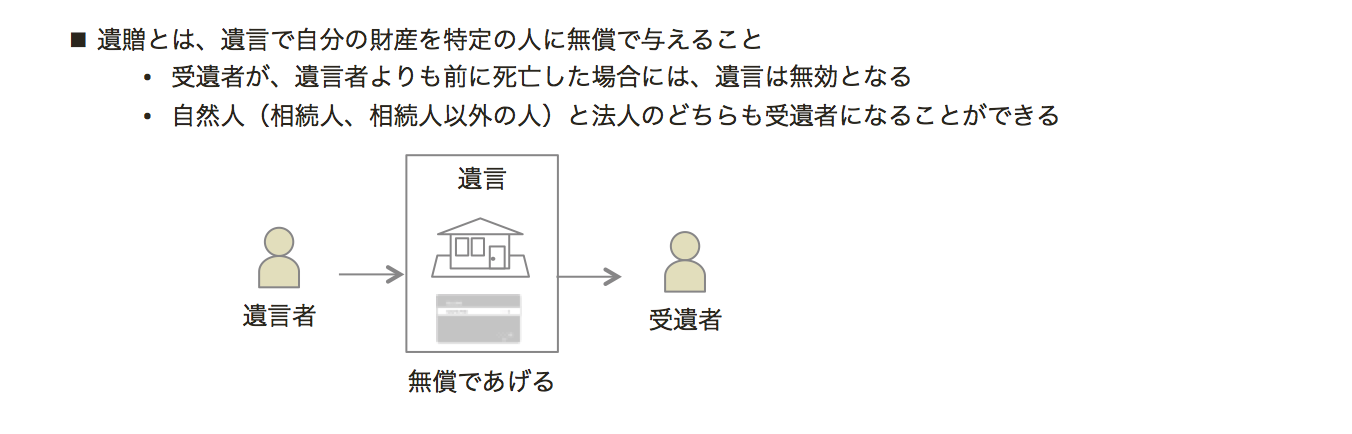
遺贈は遺言書がなければ効力が生じないのに対し、相続は被相続人の死亡によって当然に発生するという点が違います。また、遺贈は死因贈与とも類似しています。遺贈は、契約ではなく、無償の単独行為である点及び要式行為であることが死因贈与と異なります。
【相続、遺贈及び贈与の対比】
| 相続 | 遺贈 | 贈与 | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 死亡を原因として、財産が一定の親族に移転すること | 遺言によって財産を他人に無償で与えること一方的な行為 | 契約に基づいて財産を相手方に無償で与えること 「あげます」「もらいます」の一致 |
| もらう人の範囲 | 一定の親族関係 にある人 | 誰でも (法人も可) | 誰でも (法人も可) |
| 財産移転の時期 | 被相続人の死亡時 | 遺贈者の死亡時 | 随時 |
| 課される税金 | 相続税 | 相続税 | 贈与税 |
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
【包括遺贈と特定遺贈の対比】
| 包括遺贈 | 特定遺贈 | |
|---|---|---|
| 財産の指定 | 財産を特定せず割合で指定する遺贈 | 特定の財産を指定する遺贈 |
| 遺産分割方法 | 遺言と遺産分割協議 | 遺言 |
| 相続権利 | 相続人と同一の権利義務をもつ | 特定の財産を受け継ぐのみ |
| 遺産分割協議 | 参加する | 参加しない |
| 相続放棄 | 相続開始3ヶ月以内 | 意思表示のみでよい (期限なし) |
| 代襲相続 | できない | |
| 遺留分 | なし | |
包括遺贈
包括遺贈とは、例えば、「自分の財産の4分の1を○○さんに与える(又は譲る)」というように遺産を特定せずに遺産に対する割合を指定して遺贈する方法のことです。
包括遺贈により財産を取得する人を包括受遺者といいます。
包括遺贈者は相続人と同一の権利義務をもつ
包括遺贈は、実質的に通常の相続と変わらないため、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務をもちます。
ただし、相続ではなく遺贈であることから、次に示すように、包括受遺者を相続人と同じ扱いをする場合と異なった扱いをする場合があります。
相続人と同じ扱いがされるもの
- 遺産分割協議に参加する
- 遺贈の割合で債務も承継しなければならない
- 遺贈の放棄ができ、相続開始を知った日(この場合は、自己のために包括遺贈があったことを知った日)から3ヶ月以内におこなう
- 遺留分侵害請求権の相手方となる
- 負担した葬式費用を控除することができる
相続人と異なる取り扱いがされるもの
- 包括受遺者には代襲相続がない
- 包括受遺者には遺留分がない
- 相続人の誰かが相続放棄をした場合には、他の相続人の相続分は増加しますが、包括受遺者の受遺分は増加しない
- 包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない
相続税法上の取り扱いの違い
相続人以外の包括受遺者には、次の規定を適用しません。
- 相続税の基礎控除の計算上加算される相続人の数
→遺産の承継者が包括遺贈者のみで、法定相続人がゼロの場合でも、基礎控除額3,000万円を適用できる - 生命保険金等及び死亡退職金に係る非課税金額
- 相次相続控除
なお、包括受遺者が遺贈者の一親等の親族及び配偶者以外の者である場合には、相続税の2割加算の対象となります。
包括遺贈による権利義務変動の考え方(登記について)
包括遺贈による権利義務の変動は、相続という身分関係により法定された権利義務の承継ではなく、意思表示による権利義務の変動に該当します。
このため、包括遺贈される財産に不動産について包括遺贈を理由として不動産所有権の移転を第三者に対抗するためには、登記が必要です。
遺贈を原因とする所有権移転登記は、権利権利者である受遺者と、登記義務者である相続人(又は遺言執行者)との共同申請になります。
特定遺贈
具体的な財産を「与えるとか譲る」旨の遺言
特定遺贈とは、「○○の土地を△△に与える(又は譲る)」というように、遺贈する財産を具体的に指定して遺贈する方法です。特定遺贈により財産を取得する人を特定受遺者といいます。この、特定遺贈により、配偶者居住権を設定することができます。
「○○の土地を△△に相続させる」旨の遺言は、遺贈ではなく、原則として遺産分割方法の指定があったもとして取り扱います(特定財産書遺言)。
債務を負担しない
特定受遺者は、遺言書に記載された特定の財産を取得する権利があるだけで、遺言書に記載がない限り消極的な財産を負担する必要はありません。
いつでも放棄できる
特定受遺者は、相続開始後いつでも遺贈の全部又は一部を放棄することができます。また、放棄する方法が定められていないため、「遺贈を放棄します」と意思表示をするだけよく、家庭裁判所での申述も必要ありません。
特定財産承継遺言(=相続させる遺言)
「特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨」や「すべての遺産を特定の相続人に相続させる旨」の遺言(いわゆる、相続させる遺言です。改正民法では「特定財産承継遺言」として定めています。)は、遺言者の特段の意思表示がなければ遺贈ではなく、特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法の指定として取り扱います。
相続させる遺言の効果
特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定をしたものとするため、
- 遺産分割協議を経ないで、指定された相続人がその財産を取得する
- 指定された相続人が単独で相続登記ができる
となります。
遺贈する旨の遺言と相続させる旨の遺言の相違点
特定の財産を特定の相続人に遺贈する旨の遺言と相続させる旨の遺言の相違点は、次の表のとおりです。
なお、遺産分割方法の指定が、特定の財産を特定の相続人に処分させることを定めるものではなく、分割の方針(たとえば、○○は△△に委ねるなど)や手段(たとえば、財産は全て△△が取得し、□□は、代償金を支払うなど)を定めている場合は、別途、遺産分割協議を行う必要があります。
指定された受遺者が先に死亡した場合
相続させる遺言で、特定の財産を受け取るとされた受遺者が、被相続人よりも先に死亡した場合には、遺贈は無効となります。
代襲遺贈のようなことも生じません。
遺贈が無効になることを避けるには、あらかじめ、「その受遺者が先に死亡していた場合には、その受遺者の子に遺贈する旨の意思表示」を遺言書に記載しておく必要があります。このような遺贈方法を、補充遺贈といいます。
条件付遺贈
停止条件付遺贈と期限付遺贈がある
遺言者は遺贈をするにあたり、遺贈の効力の発生に条件や期限を付けることができます。
| 停止条件付遺贈 | 期限付遺贈 | |
|---|---|---|
| 遺贈の効力発生時 | 条件が成就したとき | 期限が到来したとき |
| 相続税の申告 | 未分割として申告 | |
遺贈の効力を条件に関わらせる場合を「停止条件付遺贈」、期限にかからせる場合を「期限付遺贈」といいます。遺贈の効力が生じるまでは、受遺者は、遺贈義務者に対して履行請求することができません。
例えば、孫が大学に入学することを条件に遺贈するというような条件を付けると、入学するという条件が遺贈の効力を停止しているので、停止条件付遺贈となり、孫が20歳の誕生日に遺贈するという条件を付けると期限付遺贈となります。
効力が発生する前は未分割財産として申告する
条件が成就又は期限が到来する前に相続税申告期限が到来する場合には、その遺贈の目的となっている財産は未分割財産として、法定相続分によって取得したとして申告します。
条件が成就したら更正の請求をする
その後、条件が成就した時又は期限が到来した時に遺贈の効力が発生し、相続人が有していた遺贈の目的物が受遺者に帰属します。
条件の成就により相続税が減少する相続人は、条件の成就を知った日の翌日から4ヶ月以内に限り、更正の請求ができます。
また、受遺者は、遺贈の目的となった財産を取得することになりますが、これにより新たに申告義務が生じる者は期限後申告を、納付すべき相続税が増える者は修正申告をおこないます。正当な事由による期限後申告及び修正申告に該当するため、加算税や延滞税は課税されません。
負担付遺贈
受遺者に対して一定の負担を負わせる遺贈
負担付遺贈とは、受遺者に対して一定の負担を負わせるものをいいます。例えば、「マンションをAに遺贈する。ただし、Aはローンの債務を引き継ぐこと。」などの場合です。負担させる義務は遺贈される対象とは関係がなくてもかまいません。
受遺者は、遺贈の目的となった財産の価額の範囲内で、負担した義務の履行責任を負います。受遺者は、一括してこれを承認するか又は放棄することができますが、負担だけを拒否することはできません。
受遺者が負担を履行しない場合、相続人は受遺者に対して相当の期間を定めて負担の履行を求めることができ、それでも期間内に履行されない場合には、家庭裁判所に負担付遺贈の取り消しを請求することができます。
負担によって利益を得る人も相続税の課税対象
負担付遺贈によって、その負担によって第三者に利益をもたらす場合には、その第三者が負担額に相当する金額を遺贈によって取得したものとして、相続税の課税対象となります。例えば、「マンションをAに遺贈するが、条件として、AはBに対して○○円を支払うこと」とした遺言の場合です。
負担付遺贈財産の課税価額の計算
負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈があったときに確実と認められる金額に限る)を控除した価額によるものとなっています。
なお、負担付遺贈以外は、相続人又は包括受遺者でない限り債務控除できないことになっています。
遺贈の目的となる財産の価額は、財産評価基本通達により評価した額のことで、その負担が金銭の等の資産を給付することである場合は、その負担額は遺贈があった時(相続開始時)において確実と認められる金額、債務の弁済など債務の減少をもたらす場合にはその減少する債務の額をいいます。(負担付贈与により取得した土地等及び家屋の価額は、取得時の通常の取引価額である時価評価となっているので注意しましょう。その他にも、債務の弁済を条件に財産を贈与する場合、贈与した者に譲渡があったものとみなして、所得税法において譲渡所得が課税されます。)
なお、負担付遺贈に基づく負担の利益が受益者に帰属する場合は、その受益者が負担額に相当する金額を遺贈によって取得したものとして相続税が課税されます。
さらに、譲渡所得税が課税される場合がある
負担付遺贈が特定遺贈の場合には、譲渡所得税が課税されます。
負担付贈与における負担部分が、遺贈者及び相続人に対して何らかの経済的利益をもたらす場合には、その負担に相当する経済的利益を収入金額とする
「資産の譲渡」に該当するからです。
例えば、時価1000の土地建物を遺贈するが、負債600の負担が条件となっている負担付遺贈の場合で、土地建物の取得価額が500である場合。500のものを600で譲渡することになるため、100の譲渡所得が発生します。遺贈者に対する譲渡所得であるため、準確定申告が必要となります。
また、相続税評価額800から負担額600を控除した200に相続税が課税されます。
対価を伴わない単純な個人に対する遺贈では、遺贈財産すべてについて相続税が課税され、受遺者は遺贈者の取得時期と取得価額を引き継ぎます。
これに対して、負担付遺贈は、原則として受遺者は支払った対価で当該資産を取得したことになるため、実際に支払った金額が当該資産の取得価額となります。
ただし、譲渡価額(負担付遺贈の負担額)が時価の2分の1未満であり、かつ、遺贈者の取得価額を下回る場合(譲渡損失が計上される場合)は、遺贈者の譲渡損失はなかったものとみなし、遺贈者の取得時期と取得価額は受遺者に引き継がれます。
負担付贈与との違い
これに対し、負担付贈与の場合は、贈与税の負担回避の手段として利用されることを防止するため、土地家屋の負担付贈与については、財産の評価額を相続税評価額ではなく、その取引時の通常の取引価額に相当する額である時価で評価します。
例えば、土地建物を、相続税評価額で評価することを認めると、相続税評価額と同額の銀行ローンの引き受けを条件にして贈与することで、贈与税の課税は、評価額から引き受け債務を控除することから贈与税が課税されないということになってしまうのです。
単純贈与の場合は、贈与者に所得税が課税されることはありません。個人間の贈与については、みなし譲渡課税はおこなわないからです。しかし、負担付贈与の場合は例外となっています。
【土地家屋の財産評価:贈与と遺贈の取り扱いの違い】
| 負担付贈与 | 負担付遺贈 | |
|---|---|---|
| 土地家屋の財産評価額 | 通常の取引価額(時価) | 相続税評価額 |
法人に対する遺贈
時価で譲渡があったとして取り扱う
法人に対して遺贈をすることができます。法人に対し資産の遺贈(死因贈与、贈与を含む)が行われた場合に、通常の取引価額である時価で譲渡があったものとして取り扱います。
| 遺贈者 | 受遺者(=法人) | |
|---|---|---|
| 課される税金 | 相続税 所得税 | 法人税 |
このように、法人に遺贈をすると、受遺者及び相続人の双方で税金を支払うことになります。
準確定申告が必要
遺贈者はみなし譲渡所得の申告が必要となり、遺贈者の譲渡所得税の申告は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、相続人がおこないます。これを、準確定申告といいます。
法人に寄付金課税及び法人株主に贈与税課税
法人は、法人税の計算上、取得した財産の時価を益金に算入することになります。法人が同族会社に該当し、この遺贈により株式価値が上昇した場合には、遺贈者から「法人の株主」に対して贈与があったものとして、贈与税が課税されるリスクがあります。
公益社団法人の場合には例外的な取り扱い
この受遺者となる法人が公益社団法人等の公益を目的とする事業を行う法人である場合には、公益に資することや2年以内に公益事業の目的に直接使われることなど一定の条件を満たし国税庁長官の承認を得たときには、みなし譲渡所得は課税されません。


